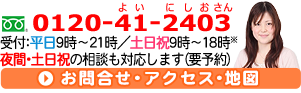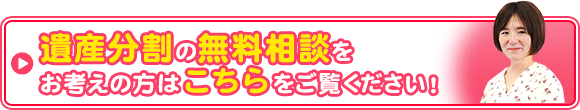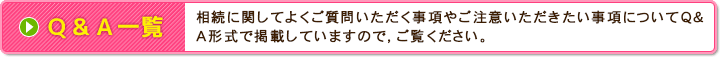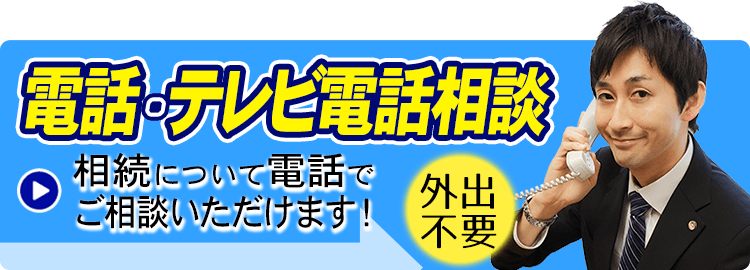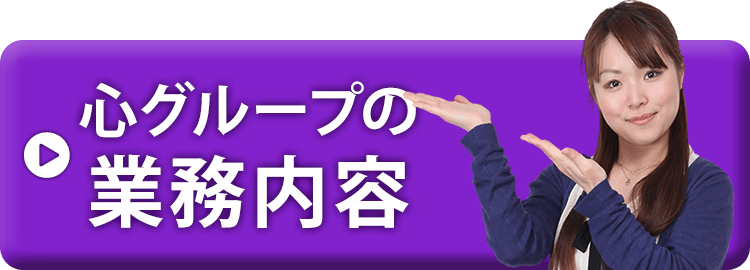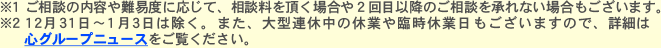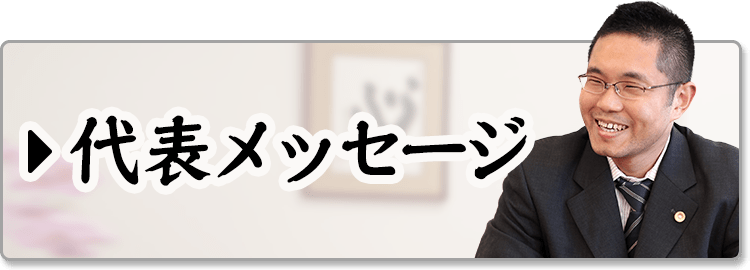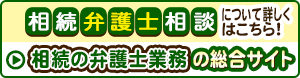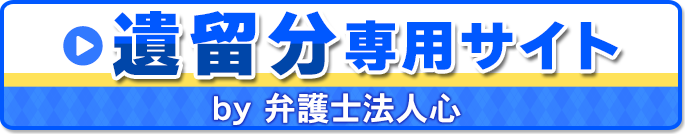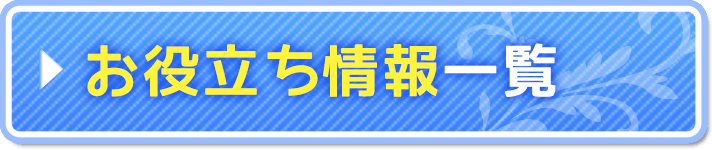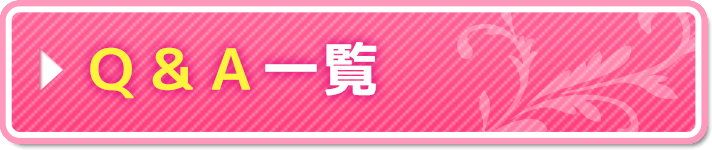遺産分割協議書を作成する際に注意すること
1 当事者の記載
前提として、遺産分割協議書を作成する際は、必ず相続人全員で行う必要があります。
相続人を除外して作成された遺産分割協議書は、原則として無効となり、除外された相続人を含めた遺産分割協議書を改めて作成し直さなければなりません。
そのため、遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員で行うよう注意が必要です。
そして、遺産分割協議書には、相続人全員が行ったことがわかるように、相続人全員の氏名、住所を記載し、署名押印も行う必要があります。
この際に注意するべきは、記載の方法です。
上に述べたように、相続人全員での遺産分割協議書作成が必須ですので、本当にその人が相続人であることを明らかにするため、相続人の氏名や住所は、住民票等の公的な文書に記載されているとおりに記載します。
また、押印についても、同様の理由から、実印で行い、印鑑登録証明書の添付も必要です。
相続人の中に未成年者がいた場合は、法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことができます(民法824条)。
しかし、ここで注意が必要なのは、親権者と未成年者が共に共同相続人であった場合、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議を行うことができないということです(民法826条)。
つまり、父、母、子(10歳)の家族がおり、父が亡くなった場合には、母が子に代わって遺産分割協議を行えないということです。
この場合には、特別代理人の選任が必要であり(民法826条1項)、親権者、上記の例では母が、子である未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない点に注意が必要です。
2 遺産の記載と分割方法の記載
遺産を記載するにあたり、誰が、どの財産を、どれだけ取得するのかを明確に記載しなければ、後日不要な紛争の種となりますので、注意が必要です。
そのため、不動産がある場合は、不動産の表示は法務局から取得した登記簿のとおりに記載します。
具体的には、土地であれば、所在・地番・地目・地積を記載し、建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿とおりに記載する必要があります。
債券や預貯金等も明確に記載するように注意が必要ですが、記載の方法に困ったら専門家に相談するとよいでしょう。
3 その他の注意点
最後に、細かい点ですが、注意する必要があることを2つ挙げたいと思います。
まず、1つ目は、協議書の作成部数です。
協議書の作成部数は、後日のトラブルを防ぐために、基本的に1通ではなく、相続人の人数分作成することをおすすめします。
また、金融機関等に手続きを行う必要がある場合には、提出する必要がある部数を追加で予め作成しておくとよいでしょう。
2つ目は、協議書が数ページになる場合は、各ページに割印をすることです。
割印がなくとも、遺産分割協議書の効力が否定されるわけではありませんが、遺産分割協議書が相続人全員により間違いなく作成されたことを証明するために、相続人全員が割印をすることをおすすめします。
なお、割印の箇所に特段決まりはありません。
生前贈与を受けた後で相続放棄をする場合の注意点 相続した家の名義変更について