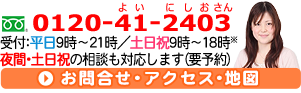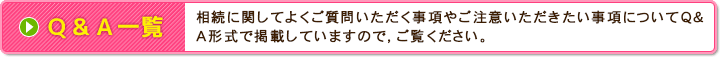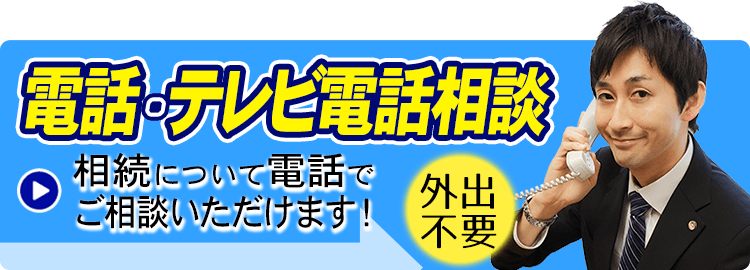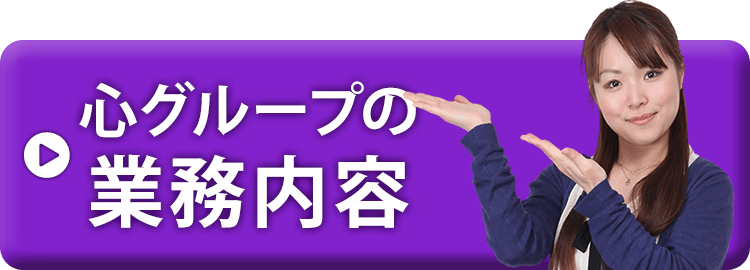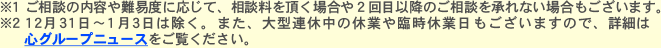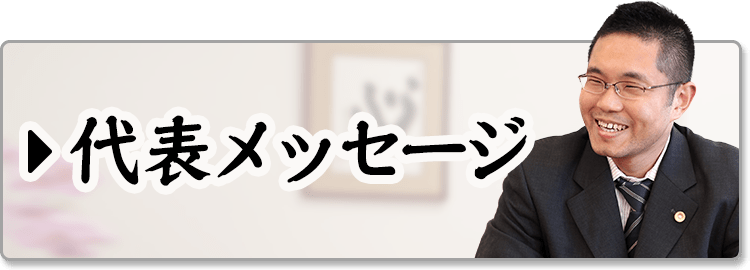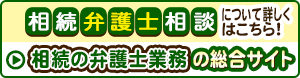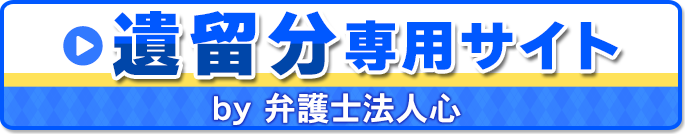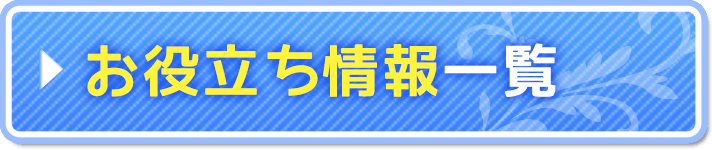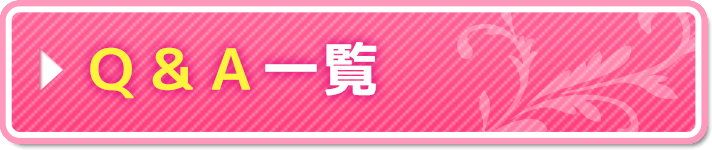遺産分割前の相続預金の払戻しについて
1 遺産分割の前に被相続人の預貯金の払戻しを受ける方法
被相続人の方がお亡くなりなり、相続が発生すると、原則として被相続人の預貯金口座は凍結されてしまいます。
かつては、遺産分割を済ませて相続手続きを終えるまで、被相続人の預貯金を引き出すことは一切できませんでした。
しかし、葬儀費や当面の生活費など、相続人が被相続人の預貯金を必要とする場面もあります。
そこで現在では、一定の条件を満たす場合に、遺産分割を終えていなくても被相続人の預貯金を引き出すことができる制度ができました。
具体的には、家庭裁判所の判断による払い戻し制度と呼ばれるものと、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度と呼ばれるものがあります。
以下、それぞれについて説明します。
2 家庭裁判所の判断による払い戻し制度
家事事件手続法第200条第3項に基づき、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申立てている場合に利用することができる制度です。
具体的には、相続人から家庭裁判所へ預貯金払戻しの申立てを行うことで、家庭裁判所による審判によって、相続預金の全部または一部の払い戻しができることになります。
払戻しができる金額については、家庭裁判所が、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁、その他の事情を考慮して判断することとされています。
【参考条文】(家事事件手続法)
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条
(第1~第2項略)
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
(第4項略)
参考リンク:e-Gov法令検索(家事事件手続法)
3 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度
民法909条の2に基づき、一定の範囲であれば、2のように遺産分割調停を申し立てて家庭裁判所による判断を経ることをしなくても、被相続人の預貯金を引き出すことができます。
具体的には、1つの金融機関あたり、次の金額のうちいずれか低い方を引き出すことができます。
①相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額
②150万円
なお、金融機関における払戻し手続きの際には、相続開始の事実と法定相続割合を証明するため、一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
【参考条文】(民法)
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)